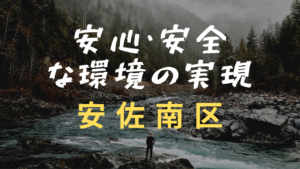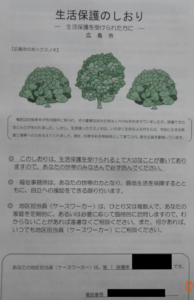自立更生計画の経費(課)第8の40
○生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日)
(社保第34号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局保護課長通知)
[参考(改正後全文)]
今般、保護基準の第19次改定等に伴ない保護の実施要領については、昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知(以下「次官通知」という。)の一部が改正されるとともに昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知(以下「局長通知」という。)が新たに定められたところであるが、これに伴ない昭和36年4月1日社保第22号本職通知を次のとおり全面改正したので了知のうえ実施要領取扱い上の指針とされたい。
また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
問40 局長通知第8の2の(3)及び(4)にいう自立更生のための用途に供される額の認定は、どのような基準によるべきか。
答 被保護世帯の自立更生のための用途に供されるものとしては、次に掲げる経費にあてられる額を認めるものとすること。これによりがたい特別の事情がある場合は、厚生労働大臣に情報提供すること。
なお、この場合、恵与された金銭又は補償金等があてられる経費については、保護費支給又は就労に伴う必要経費控除の必要がないものであること。
(1) 被保護者が災害等により損害を受け、事業用施設、住宅、家具什器等の生活基盤を構成する資産が損われた場合の当該生活基盤の回復に要する経費又は被保護者が災害等により負傷し若しくは疾病にかかった場合の当該負傷若しくは疾病の治療に要する経費
(2) (1)に掲げるもののほか、実施機関が当該被保護世帯の構成、世帯員の稼働能力その他の事情を考慮し、次に掲げる限度内において立てさせた自立更生計画の遂行に要する経費
ア 当該経費が事業の開始又は継続、技能習得等生業にあてられる場合は、生活福祉資金の更生資金の貸付限度額に相当する額
イ 当該経費が医療にあてられる場合は、医療扶助基準による医療に要する経費及び医療を受けることに伴って通常必要と認められる経費の合算額
ウ 当該経費が介護等に充てられる場合は、生活福祉資金の療養・介護資金の貸付限度額に相当する額
エ 当該経費が家屋補修、配電設備又は上下水道設備の新設、住宅扶助相当の用途等にあてられる場合は、生活福祉資金の住宅資金の改修費の貸付限度額に相当する額
オ 当該経費が、就学等にあてられる場合は、次に掲げる額
(ア) 当該経費が幼稚園等での就園にあてられる場合は、入園料及び保育料その他就園のために必要と認められる最小限度の額
(イ) 当該経費が義務教育を受けている児童の就学にあてられる場合は、入学の支度、学習図書、運動用具等の購入、珠算課外学習、学習塾費等、修学旅行参加等就学に伴って社会通念上必要と認められる用途にあてられる最小限度の実費額
(ウ) 当該経費が高等学校等、夜間大学又は技能修得費(高等学校等就学費を除く)の対象となる専修学校若しくは各種学校での就学にあてられる場合は、入学の支度及び就学のために必要と認められる最小限度の額(高等学校等の就学のために必要と認められる最小限度の額については、学習塾費等を含む。貸付金については、原則として、高等学校等就学費の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む。)及び高等学校等就学費の基準額でまかないきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額にあてられる場合に限る。)
(エ) 当該経費が大学等への就学後に要する費用にあてられる場合は、授業料や生活費その他就学のために必要と認められる最小限度の額(当該取扱いは、大学等への就学後に要する費用にあてることを目的とした貸付金や恵与金を当該大学等に就学する者が高等学校等に在学している間に、同一世帯の被保護者が受領する場合に限る。)
カ 当該経費が、結婚にあてられる場合は寡婦福祉資金の結婚資金の貸付限度額に相当する額
キ 当該経費が弔慰に当てられる場合は、公害健康被害の補償等に関する法律による葬祭料の額
ク 当該経費が、当該世帯において利用の必要性が高い生活用品であって、保有を容認されるものの購入にあてられる場合は、直ちに購入にあてられる場合に限り、必要と認められる最小限度の額
ケ 当該経費が通院、通所及び通学のために保有を容認される自動車の維持に要する費用にあてられる場合は、当該自動車の利用に伴う燃料費、修理費、自動車損害賠償保障法に基づく保険料、対人・対物賠償に係る任意保険料及び道路運送車両法による自動車の検査に要する費用等として必要と認められる最小限度の額
コ 当該経費が国民年金受給権を得るために充てられる場合は、国民年金の任意加入保険料の額
サ 当該経費が次官通知第8の3の(3)のクの(イ)にいう「就労や早期の保護脱却に資する経費」に充てられる場合は、本通知第8の58の2の2の(1)から(6)までのいずれかに該当し、同通知の取扱いに準じて認定された最小限度の額
シ 厚生年金の受給権を得たために支払う必要が生じた共済組合等から過去に支給された退職一時金の返還額
ス 当該経費が、養育費の履行確保にあてられる場合は、養育費の取決めに関する公正証書や調停申立て等に要する費用、養育費に係る保証サービスを利用した際の保証料に要する費用等として必要と認められる最小限度の額
(3) 成年後見人、保佐人、補助人の申立てや報酬のために必要な経費。ただし、この取扱いに当たっては、自立更生計画の策定を要しないこととする。
※ エクセルの表にしてみました。
| 項目番号 | 経費の用途 | 認定の基準や限度額 |
|---|---|---|
| 1 | 災害等により生活基盤が損われた場合の回復に要する経費 | 必要な実費 |
| 2-ア | 事業開始、継続、技能習得等 | 生活福祉資金の更生資金の貸付限度額相当額 |
| 2-イ | 医療 | 医療扶助基準に基づく経費 + 通常必要と認められる経費 |
| 2-ウ | 介護等 | 生活福祉資金の療養・介護資金の貸付限度額相当額 |
| 2-エ | 家屋補修、配電設備や上下水道設備の新設等 | 生活福祉資金の住宅資金の改修費の貸付限度額相当額 |
| 2-オ(ア) | 幼稚園等での就園 | 入園料、保育料など就園に必要な最小限度の額 |
| 2-オ(イ) | 義務教育を受けている児童の就学 | 必要な実費 |
| 2-オ(ウ) | 高等学校や専修学校での就学 | 最小限度の必要額 |
| 2-オ(エ) | 大学等への就学後に要する費用 | 授業料、生活費等、最小限度の必要額 |
| 2-カ | 結婚 | 寡婦福祉資金の結婚資金の貸付限度額相当額 |
| 2-キ | 弔慰 | 公害健康被害の補償等に関する法律の葬祭料の額 |
| 2-ク | 高い必要性が認められる生活用品の購入 | 必要最小限度の額 |
| 2-ケ | 自動車の維持に必要な経費 | 燃料費、修理費、保険料、車検費用等、最小限度の額 |
| 2-コ | 国民年金受給権を得るための任意加入保険料 | 国民年金の任意加入保険料の額 |
| 2-サ | 就労や早期の保護脱却に資する経費 | 通知第8の58の2の取扱いに準じた最小限度の額 |
| 2-シ | 厚生年金の受給権取得による退職一時金の返還 | 必要な返還額 |
| 2-ス | 養育費の履行確保 | 公正証書や調停申立費用、保証料等、最小限度の額 |
| 3 | 成年後見人等の申立てや報酬 | 必要な経費(計画の策定は不要) |
参考*出典不明ですが、参考にしてみてください。
| 区分 | 内容 | 金額の基準 | 金額 | 事例 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 災害等により損害を受け、生活基盤を構成する資産が損われた場合 | 当該生活基盤の回復に要する経費 | 必要な経費 | 家財道具、住宅確保費用、事業再開費用 | 家具什器費の基準額(40000円)ではない |
| (1) | 負傷・疾病による治療に要する経費 | 保険診療以外の費用が含まれる | 必要な経費 | 医療費 | |
| (2)ア | 事業の開始・継続・技能習得等に要する経費 | 生活福祉資金の更生資金の貸付限度額 | 130-580万円 | 店舗、設備、機械、器具等の購入や整備費用 | 障害者の通勤用車両購入費や資格取得費も含む |
| (2)イ | 医療に要する経費 | 医療扶助基準+移送費 | 必要な経費 | 通院の交通費 | 自家用車のガソリン代や駐車場代も考慮される |
| (2)ウ | 介護等に充てられる経費 | 生活福祉資金の療養・介護資金の貸付限度額 | 170-230万円 | トイレ改修、介護用品、ヘルパー費用 | |
| (2)エ | 家屋補修・設備新設等に要する経費 | 生活福祉資金の住宅資金の改修費 | 250万円 | 畳、水道設備、配電設備、便所設置など | |
| (2)オ(ア) | 幼稚園等での就園に要する経費 | 入園料、保育料など | 必要な経費 | 保育料控除も適用可能 | |
| (2)オ(イ) | 義務教育就学に要する経費 | 最小限度の実費 | 必要な経費 | 塾費用、問題集、通学用自転車など | |
| (2)カ | 結婚費用 | 寡婦福祉資金の貸付限度額 | 300,000円 | 挙式披露費用、新居準備費用 | |
| (2)キ | 弔慰費用 | 葬祭料の額 | 651,000円 | 墓石購入、仏壇購入、永代供養費用など | |
| (2)ク | 生活用品購入費 | 必要と認められる最小限度の額 | 必要な経費 | 家財道具、電化製品、かばん | |
| (2)ケ | 自動車の維持費 | 燃料費、修理費、自賠責保険料など | 必要な経費 | 通院や通勤に必要な場合 | |
| (2)コ | 国民年金受給権の取得費 | 国民年金の任意加入保険料 | 約175万円 | 未払期間分10年支払い可能 | 保護費が減る可能性 |
私的におすすめ動画がありましたので、紹介します。
⬇️ ⬇️ ⬇️
障害×仕事×自立の相談窓口 アイワークスチャンネル
•チャンネル登録者数 2480人
•788 本の動画